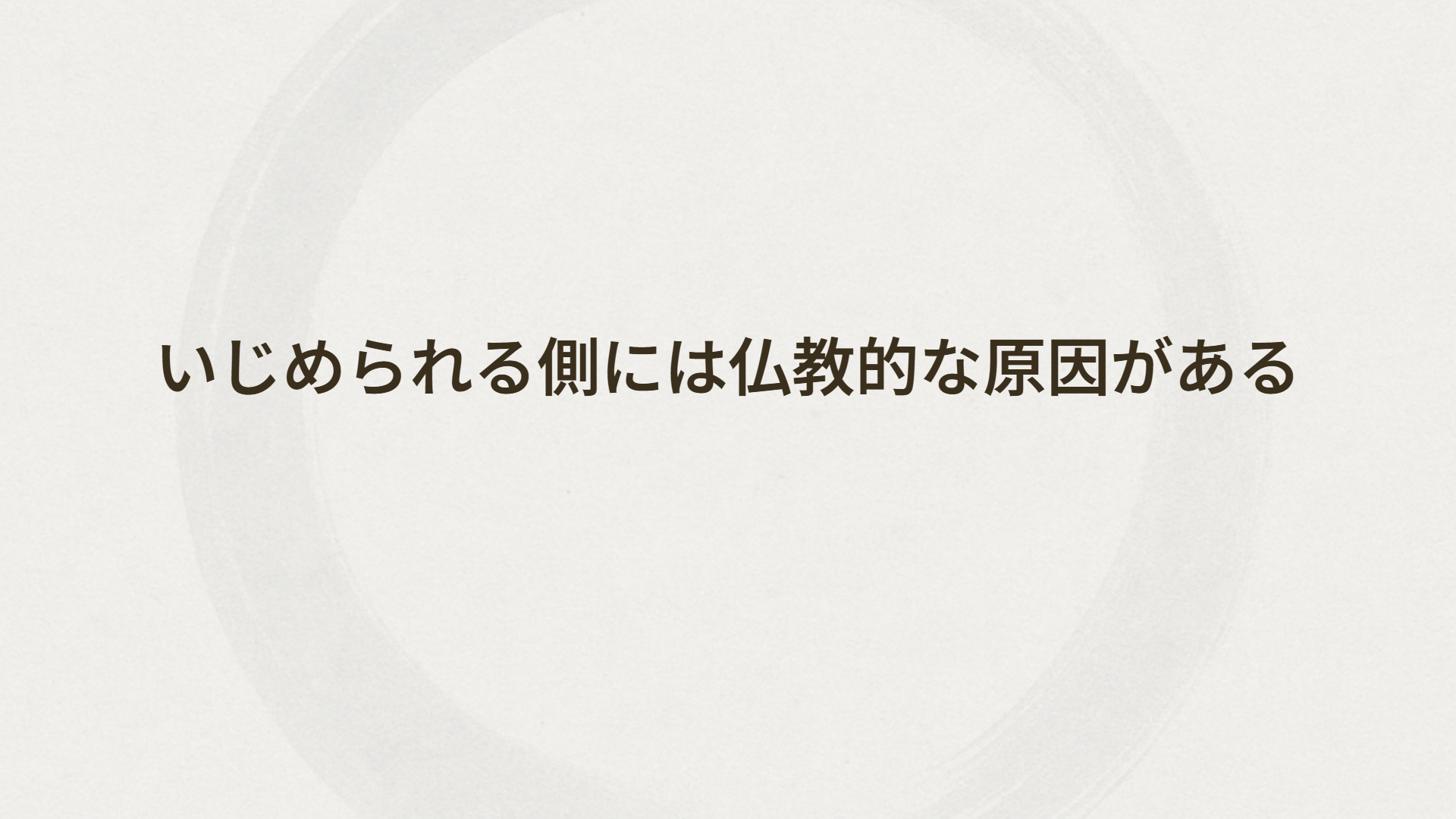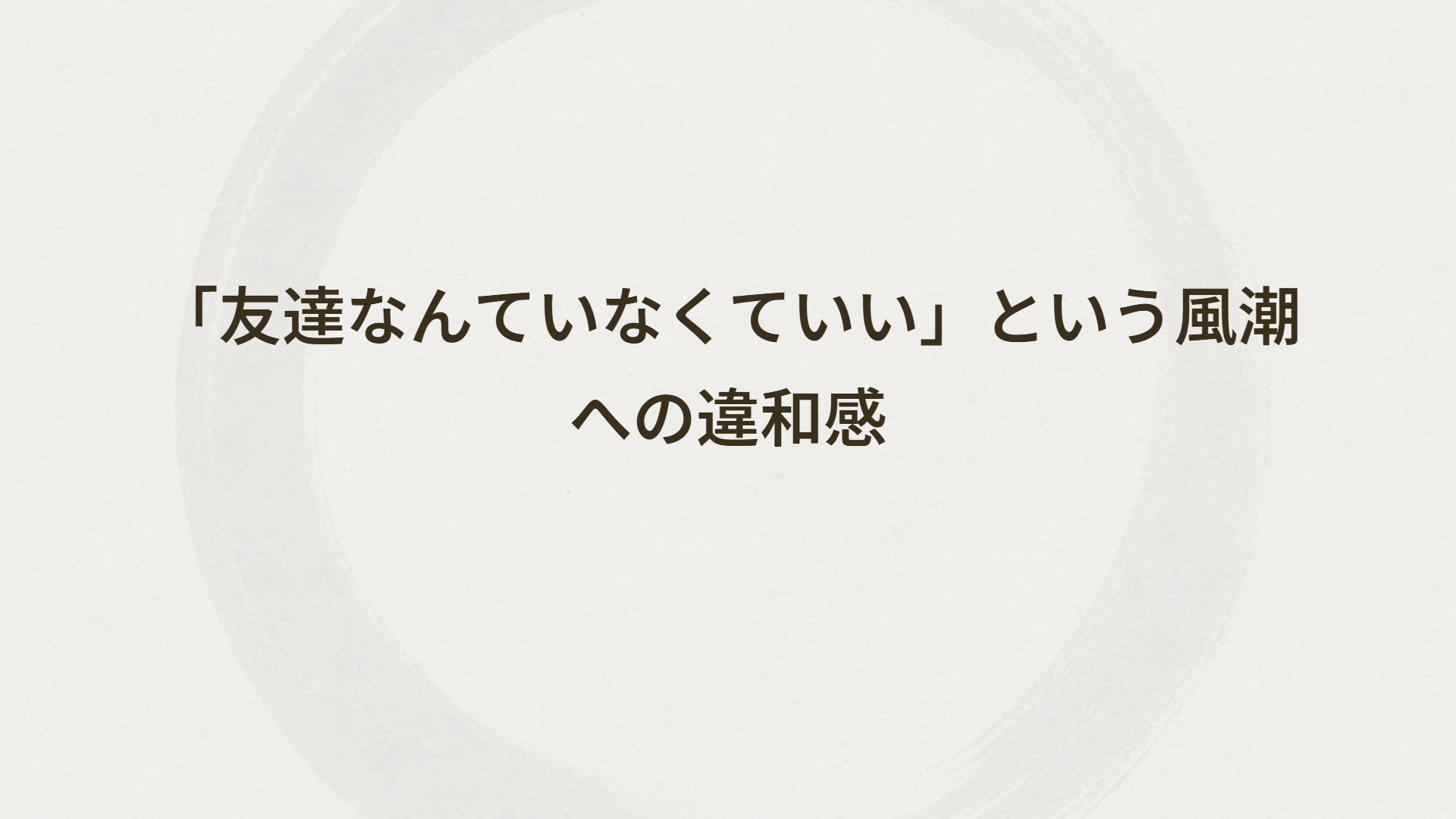お葬式の一般焼香中にお経を読まない理由
当寺では、葬儀において「親族焼香」と「一般焼香」とを明確に分けている。読経の後、親族の焼香が終わると、僧侶と親族は一度退堂し、その後に一般参列者による焼香を行うという流れである。
この方法は、先代住職の代から続くものであるが、最近改めてその意義を深く実感する出来事があった。
儀式と告別を分けるという考え方
通夜や葬儀といった法要には、「儀式」と「告別式」という二つの側面がある。
儀式とは、故人が仏の道を歩み、成仏されることを願う仏事であり、僧侶の読経の中で遺族や親族が共に祈りを捧げる厳粛な時間である。一方、告別式は、参列者がそれぞれの想いで故人に別れを告げる場であり、その性質は異なる。
この二つを明確に分けることで、儀式の本来の意義が損なわれず、告別の時間も落ち着いて過ごすことができる。
読経はBGMではない
昨今、読経を「儀式のBGM」と捉える人が少なくない。焼香の間に何となく流れている音のように感じてしまうのかもしれない。
しかしながら、読経は単なる雰囲気づくりのための音ではない。故人の成仏を願うために僧侶が心を込めて唱える仏の言葉であり、それ自体が葬儀の中核である。読経の意味を軽んじてしまえば、葬儀は単なる形式的な儀礼に堕してしまう。
儀式中に一般焼香が始まると、読経の意味が見失われ、参列者は焼香の順番や挨拶に意識を奪われてしまう。その結果、本来集中すべき読経の場が「背景音」と化してしまうことがある。
焼香のタイミングがもたらす空気
実際、先日ある葬儀において、司会との打ち合わせ不足により、親族焼香の直後に一般焼香が始まってしまった。すると会場が一気にざわつき、儀式に集中できる空気が損なわれてしまった。
葬儀の空間において、音や動きが与える影響は大きい。焼香の移動や人の気配が増えることで、場の静けさと厳粛さは容易に失われるのである。
改めて感じたこと
これまでは「親族焼香と一般焼香を分けるのが当寺の慣習」という程度の意識であった。しかしながら、上記の出来事を通じて、「儀式にふさわしい静謐な空間を守ること」の意義を強く感じた。
葬儀とは、故人と向き合い、祈りの中で別れを告げる場である。そのためには、儀式と告別、それぞれの時間を明確に分け、その意味を丁寧に守る必要がある。
当寺では、今後もこのやり方を大切に継承し、参列される方々にもその意義を伝えていきたいと考えている。