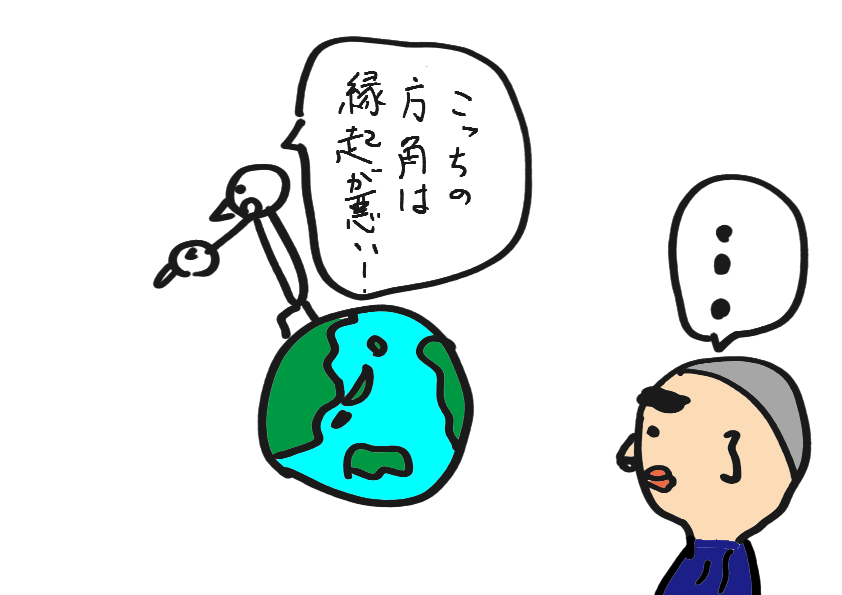お釈迦様は、なぜお金を持たなくても生きられたのか
現代の感覚でいえば、「お金を持たずに生きる」というのは無謀であるように思える。しかし、お釈迦様は確かにお金を持たず、托鉢によって生きていた。そして、その生活に揺るぎない信頼を置いていた。
では、なぜそれが可能だったのか。
—
人間の中に「施したい心」があるという信
お釈迦様は、人間には本来的に「与えたい」「役に立ちたい」という心があると見ていた。そして托鉢とは、出家者が一方的に受け取る行為ではなく、**施す者に「善行の機会」を与える行為**でもある。
「もらう側」と「与える側」は、互いに修行の道を歩んでいるというわけだ。
—
托鉢は文化ではなく、在り方の表現
釈尊の時代、托鉢は社会に根付いた文化でもあったが、それ以上に重要なのは、出家者の在り方である。誠実に、無欲に、慈悲をもって生きるその姿が、自然と周囲の人々の心に何かを触れさせたのだ。
お金を持たないという選択は、無防備ではない。むしろそれは、「この世界は信頼に値する」と言い切る生き方だった。
—
禅的な見方――乞うこと自体が修行
禅の伝統においても、托鉢は「もらう」ためではなく、「乞う」こと自体が修行であるとされる。たとえ誰も布施してくれなくても、その行為に身を置き続けることに意味がある。
それは、「乞う自分」と向き合い、「足ることなさ」を抱えながら、なお生きるという覚悟のあらわれである。
—
釈尊の托鉢は、信と覚悟の象徴
釈尊の生き方は、単なる他力本願ではない。「私はこの世界の善意を信じる。だから私は乞う。」という、深い信と覚悟に裏打ちされていた。
現代の私たちにとって、これは非常に示唆に富む。
私たちもまた、「与えられるだろう」と信じて何かを始めることがあるだろう。そのとき、釈尊のように人間の可能性と善性を信じ抜けるかどうかが問われているのかもしれない。
—
お金に頼らないというより、信に生きる
お金を持たないとは、経済的に乏しいということではなく、「信とつながりによって支え合う生き方**」への選択である。
つまり、釈尊の托鉢とは、「お金のない生活」ではなく、「信に満ちた生活」だったのだ。