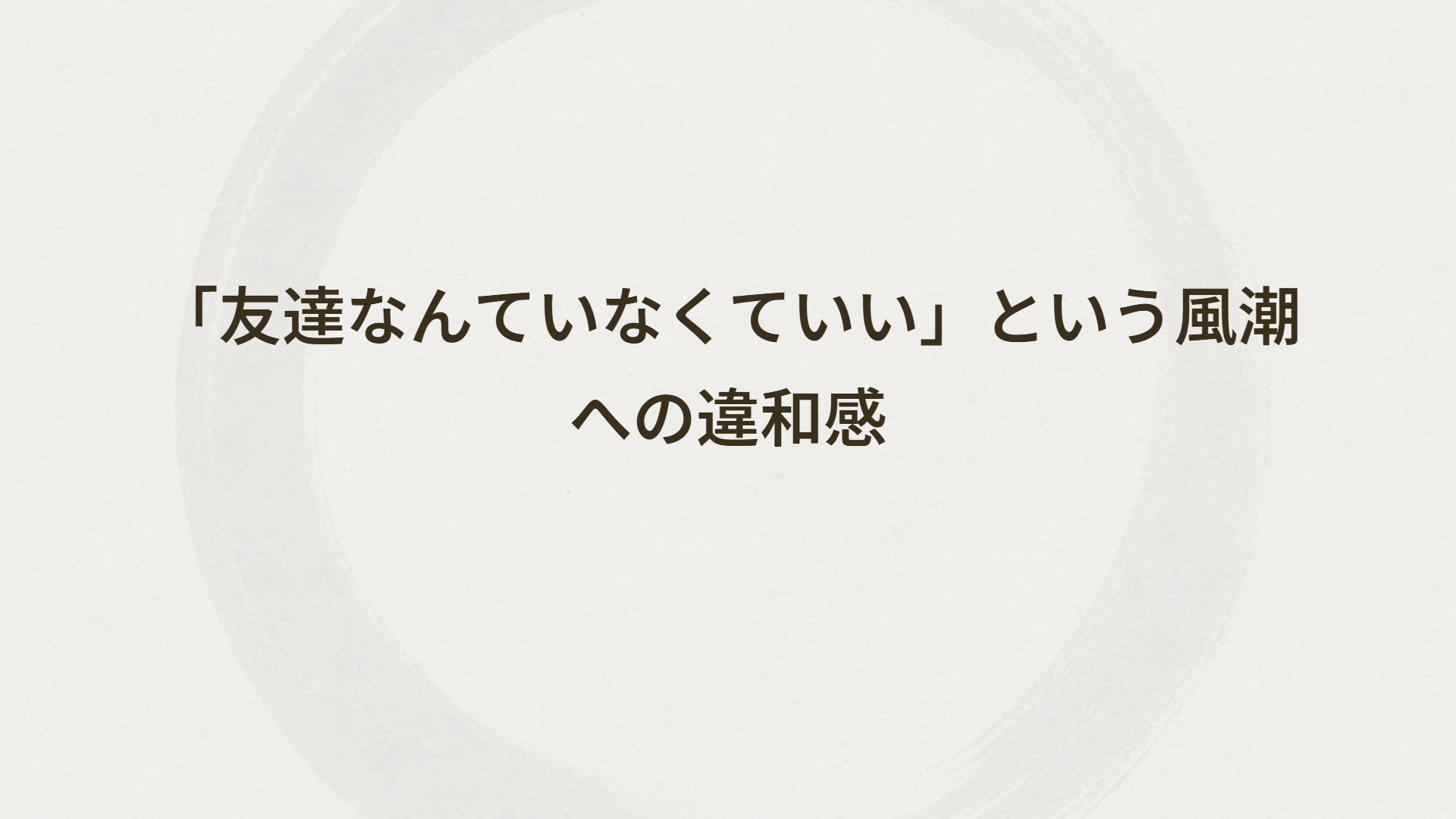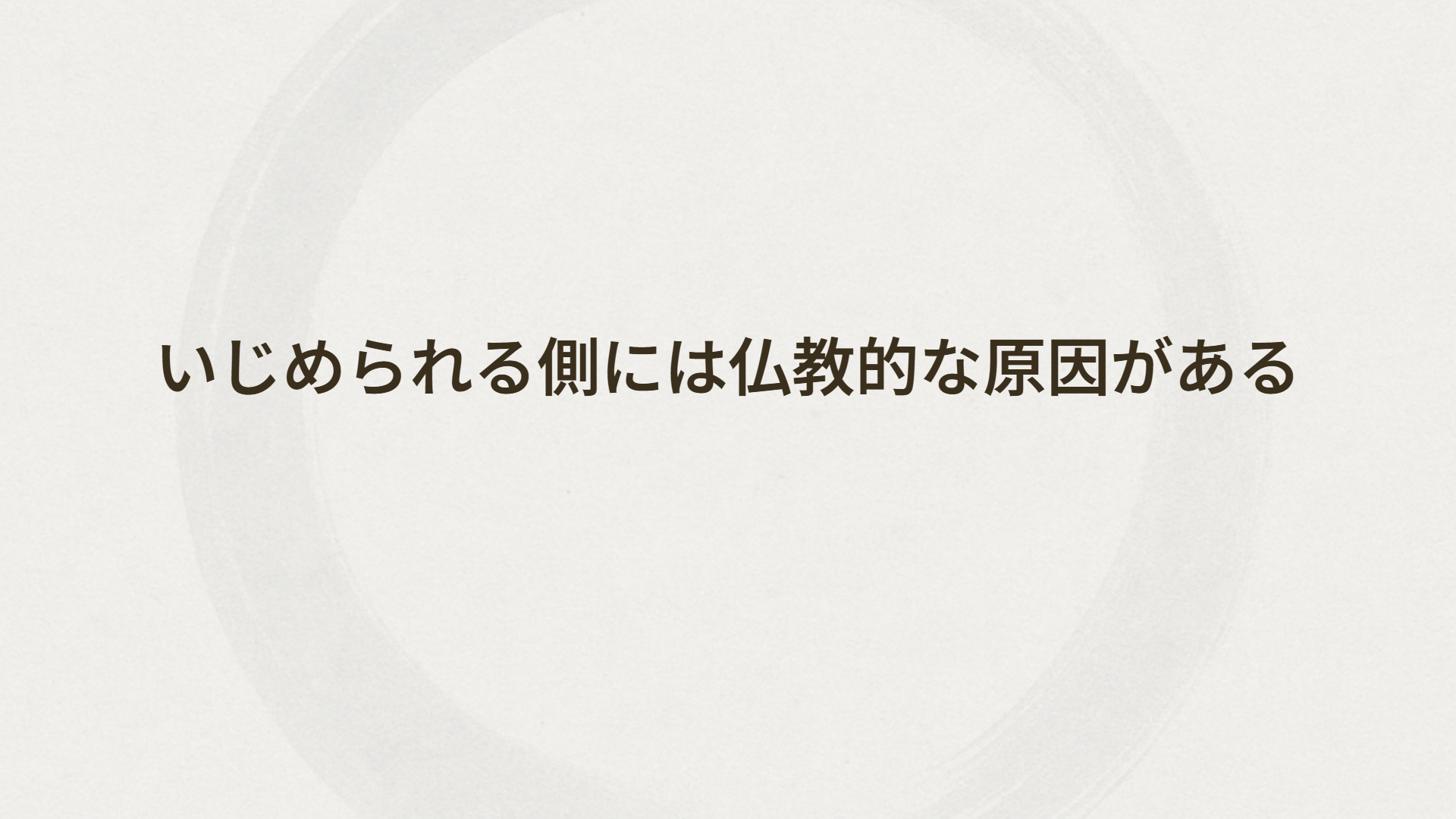四苦八苦の「生苦」を考える
仏教では、人間の苦しみを「四苦八苦」と呼ぶ。その中に「生・老・病・死」という四つの根本的な苦が含まれているが、「老・病・死」は実感しやすい一方で、「生(しょう)」を苦とすることに対しては、疑問を抱く人も少なくない。
生まれることは、本来祝福や奇跡とされるものではないのか。なぜそれが「苦」なのか──。
仏教における「苦」の意味
まず確認しておきたいのは、仏教における「苦」という言葉の意味である。
パーリ語で「苦」は「dukkha(ドゥッカ)」といい、その意味は単なる「痛み」や「辛さ」にとどまらない。dukkhaとは、不完全さ・不安定さ・無常さ・思い通りにならない性質そのものを指している。
すなわち、「苦しみ」とは必ずしも「苦痛」ではなく、コントロールできない状態や、自己の意志を超えた変化に翻弄されることそのものが「苦」なのである。
「生」の苦しみの一般的な解釈
「生」が苦であるという説明として、一般的には「産道を通る苦しみ」が語られることがある。
仏典の中には、胎内の不浄や誕生の際の苦痛を詳細に描写したものも存在し、それが「生の苦」の一つとして捉えられる場合がある。
しかし、このような説明には限界がある。なぜなら、私たちは誰一人としてその時の記憶を持っていないし、それを「苦しかった」と自覚的に語れる人はいないからである。
そのため、「生の苦」を肉体的な痛みの記憶に結びつける解釈は、現代人にとっては腑に落ちにくい側面がある。
選べないことの苦しみとしての「生」
私自身は、「生」の苦しみとは何よりもまず、「選べないこと」にあると考えている。
人は、自分の意思で生まれてきたわけではない。生まれる場所も、国も、性別も、肌の色も、時代も、親も、宗教も、すべて与えられてしまう。しかも、それらは自らの人格や生き方に多大な影響を与えるにもかかわらず、当人には一切選択権がない。
生とは、最初から無数の与件に巻き込まれている状態であり、それはまさに「dukkha」の本質──思い通りにならぬ、不安定で、自由でない状態そのものである。
仏教の縁起と無我に照らして
仏教では、あらゆるものは縁(条件)の集合によって成り立つと説かれる。これを「縁起(えんぎ)」といい、そこに独立した実体としての「自分(アートマン)」は存在しないとするのが「無我(むが)」の教えである。
この視点に立てば、生まれたという事実はすでに「縁によって成り立つ存在」としての自分を前提とし、そこには何一つ自由に選び取ったものがない。
「私とは何か」と問うたとき、そこには「私が選ばなかったもの」の集積があるにすぎない。
それが、「生」という苦しみの根本にある。
苦から出発する理由
仏教が「苦」から教えを始めるのは、それが悲観の哲学だからではない。むしろ、苦を見つめることによって、その原因を明らかにし、そこから解放される道を示すという、極めて実践的な思想だからである。
「生まれてしまった」というどうにもならない現実を、言い換えれば「選べなかった」という状態を、受け止めること。
そこから、「では、この与えられた条件のなかで、どう生きるか」と問い直すこと。
それこそが、仏教の修行の第一歩なのだと感じている。
結びに
「生まれること」は、ただ喜ばしいことでもなければ、ただ悲しいことでもない。それは、選択不可能な条件に巻き込まれているという事実そのものであり、だからこそ苦である。
その「苦しみ」を避けるのではなく、真正面から見つめ直すこと。
それこそが、仏教が説く「生きる智慧」の始まりなのである。